
こんにちは! 料理家の美窪たえです。本日は、身近な材料を使った「上海風焼きそば」の作り方をご紹介します。

日本で親しまれている上海風焼きそばといえば、オイスターソースが効いた味わいが一般的ですが、今回はあえてオイスターソースを使わず、隠し味にアンチョビを使った奥深い味わいの上海風焼きそばのレシピをご紹介していきます。

また、焼きそば麺に「3ステップの下処理」を施すことで、いつもと一味違う麺のうまさを引き出すコツもお伝えします。
最後に上海風焼きそばとセットでおすすめしたい、超簡単「町中華風スープ」の作り方もご紹介していますので、ぜひ参考に作ってみてください。それでは早速作り方に移っていきます。
材料(1人前)

- 焼きそば麺(太麺)……1玉(150g)
- 乾燥キクラゲ……4〜5個
- もやし……1/3袋(60g)
- キャベツ……葉1〜2枚(60g)
- 人参……1/6本(40g)
- ニラ……3本(30g)
- 豚バラ肉薄切り……70g
- 冷凍むきエビ……5個
- サラダ油……大さじ1
- 醤油……大さじ1
- アンチョビ……1〜2枚(3〜6g)
- おろしにんにく……小さじ1
- 砂糖……小さじ1
- 紹興酒(または日本酒)……大さじ1
- こしょう……適量
- ごま油……小さじ1
上海風焼きそばの作り方 下準備(具材)編
まず、具材の準備から始めていきます。

1.器に乾燥キクラゲと水(分量外)を入れ、戻していきます。水は乾燥キクラゲが浸る程度入れてください。
乾燥キクラゲは、水に浸けて冷蔵庫で一晩寝かせ、時間をかけてしっかり戻すと食感や大きさに躍動感が出てきます。もし時間がなければ、ぬるま湯(分量外)に浸けると15〜30分で、使えるくらいまで柔らかくなります。

乾燥キクラゲがたっぷりと水を吸ったら、ひと口サイズに切っておきます。水で戻すと10倍程度まで大きくなりますので、分量には気をつけてください。

2.キャベツと人参は1.5cm幅程度に、ニラは5cm程度にカットしておきましょう。食べごたえがあるように大きめにカットすることもできますが、今回は主役となる焼きそば麺と一緒に食べやすくなるサイズにカットしています。
豚バラ肉は4cm幅程度に切り、冷凍むきエビは水(分量外)に入れて解凍したあと、背わたがあれば楊枝などを使って取り除き、水気をふき取っておいてください。
※ニラは火の通りがとても早いので、他の具材とは別にしておくと炒める時にスムーズです。

3.もやしの下処理としてヒゲ根を取っていきます。もやしからひょろりと伸びているのがヒゲ根になります。
安価で料理にそのまま使える手軽さが売りのもやしなので、ヒゲ根を取る作業は面倒に感じられるかもしれません。ですが、丁寧にヒゲ根を取り除くことで、見た目が良くなることに加え、食感もすっきりとして段違いに良くなり、存在感が際立ちます。時間と余裕がある方はぜひやってみてください。

もやしの急に細くなっているところから先を取り除くように、指先でプチッとヒゲ根をむしり、ボウルに入れた水(分量外)に浸しておきます。元々ヒゲ根のないきれいなものは、何もせず水に浸けておきましょう。
使用するもやしは、1人前でひとつかみ程度ですので、ヒゲ根取りは必要な分だけで構いません。残ったもやしは、野菜炒めやナムルなど他の料理にお使いください。

▲左:下処理をしていないもやし 右:ヒゲ根を取ったもやし
また、「ヒゲ根を取り除く時間がない……」「ヒゲ根を取るのは面倒……」という方は、もやしを水(分量外)に15分程度浸けてみてください。これだけでも、もやしがシャキッとするので、炒めたあとの食感に違いが出ますよ。
上海風焼きそばの作り方 下準備(焼きそば麺)編

続いて、上海風焼きそばのメインとなる焼きそば麺に3ステップの下処理をしていきます。ちょっとした工夫を3つ重ねることで、焼きそば麺に段違いの存在感が出てきます。
そして、麺の太さには好みがあるかと思いますが、太めのものを選んでいただくと今回のレシピの味付けによく合いますよ。

1.焼きそば麺をお湯(分量外)で茹でていきます。
「焼きそば麺を茹でること」が下処理の第1ステップになります。鍋に湯を沸かして焼きそば麺を投入し、箸でほぐしながら1分程度茹でたらザルで湯切りします。
市販されている焼きそば麺は、一般的には一度蒸されて包装された状態で、弾力のある食感が特徴です。
ただ、焼きそば麺は茹でることで、なめらかでしっとりとした食感に変化します。加えて、お湯で茹でることで、表面にコーティングされている油が落ち、調味料の色や風味が焼きそば麺に入りやすくなるんです。

2.湯切りした焼きそば麺をバットなどに入れ、醤油をまぶします。
下処理の第2ステップは、「焼きそば麺への事前の味付け」です。今回ご紹介する上海風焼きそばのレシピでは、炒める時ではなく、事前に麺自体に醤油を馴染ませておきます。この段階で料理の味付けは9割方完了している点も、このレシピの大きな特徴です。

3.醤油が染み込んだ焼きそば麺をフライパンで焼いていきます。
第3ステップは「焼きそば麺のみで事前に焼くこと」です。フライパンにサラダ油(大さじ1/2)を入れ中火で温め、焼きそば麺だけを先に焼いていきます。
事前に醤油を染み込ませた焼きそば麺をフライパンで焼いていくことで、焼きそば麺自体に香ばしさと上海風焼きそば独特の黒い色味をまとい、見た目も味わいもグッとおいしくなります。

醤油が焦げる香りがキッチン全体に広がり、焼きそば麺にツヤが出て軽く焦げ目がついたら、いったんバットなどに取り出しておきましょう。
※焼きそば麺を焼いたあとのフライパンは、このあと使用していきますので、この時点では洗わないようにしてください。
「焼きそば麺の下茹で」「焼きそば麺への事前味付け」「焼きそば麺の焼き」という3ステップの下処理を行うことで、いつもの焼きそばとは全く違う仕上がりになります。少し時間と手間がかかりますが、おいしい上海風焼きそばを作るために、ぜひやってみてください。
上海風焼きそばの作り方 仕上げ編
具材と焼きそば麺の準備が整ったところで、仕上げの工程に入っていきます。ここから先はあっという間ですので、用意した材料を手に取りやすいところにそろえておいてくださいね。

1.焼きそば麺を調理したフライパンにサラダ油(大さじ1/2)を足し、アンチョビ、砂糖、おろしにんにくを入れて弱火にかけます。じわじわと沸いてきたら、3分程度炒めて香ばしさを引き出します。
「上海風焼きそばにアンチョビ……?」と思われたかもしれませんが、アンチョビは、魚を塩漬けにして熟成させたうま味のかたまり。さまざまなジャンルの料理に隠し味として使ってみると、魚の強いうま味が味に深みを与えてくれますよ。

また砂糖もこの段階で投入して加熱することでカラメル化を促し、独特の香ばしさを引き出します。中国の醤油は甘味があるものが多いので、砂糖を加熱することにより本場の味わいを演出できます。

2.アンチョビや調味料が程よく熱されてきたら、豚バラ肉とエビを加え中火で焼きます。
この時、あまり具材をいじらずに焼くイメージで加熱してみてください。エビは加熱しすぎると小さく硬くなってしまうので、両面の色が赤く変わったら、焼きそば麺の上に取り出しておいてください。

3.エビを取り出したら、人参、キャベツ、キクラゲを投入し、塩ひとつまみ(分量外)を入れて炒めます。この塩は、野菜の水分を引き出して火の通りを加速してくれます。味付けではないので、少量で大丈夫です。

先程と同様に、野菜を投入したらいじらず、時間を置きながら混ぜる程度で調理してみてください。炒めるという語感にとらわれず、材料を鍋肌の熱に触れさせてしっかり温度を上げていくようにすると、普段の野菜炒めも水気が出にくく上手に仕上がりますよ。

4.キャベツがしんなりとしてきたら、水気を切ったもやしを入れサッと炒め合わせます。ヒゲ根を取り水に浸けておいたもやしは、ピンと張りがあり、違いを感じていただけると思います。

5.焼きそば麺とエビをフライパンに戻したら、焼きそば麺に紹興酒(または日本酒)をふりかけて、具材と絡めながら炒めていきます。

ここで使うお酒は、紹興酒を使うと本場感が一層高まるのでおすすめです。焼きそば麺は事前に焼いてありますので、紹興酒で風味を加えつつ、温まって具材と絡めば十分です。

6.火の通りの早いニラを加え、こしょう、香りづけのごま油を回し入れ、全体を大きく混ぜ合わせれば、美窪流上海風焼きそばの完成です!
上海風焼きそばの楽しみ方

まず、できあがった上海風焼きそばを見ていただくと、黒々としなやかな焼きそば麺と具材のコントラストを感じていただけるのではないでしょうか? 醤油で黒い色がついているのは焼きそば麺だけで、具材はほぼ素材そのままの色なので、見た目の色鮮やかさが際立ちます。

ひと口食べてみると、まずなめらかで奥深い味わいの焼きそば麺の存在を感じていただけるかと思います。事前に醤油で下味をつけて香ばしく焼き上げた麺に、アンチョビと加熱した砂糖の香ばしさやコクが合わさり、濃厚な味わいになっています。
また、焼きそば麺と一緒に食べやすいサイズにカットした各具材は、食べるごとに食感の変化があり、箸が進みますよ。
もやしの下処理や各工程でひと工夫を挟みますが、丁寧に行えばおいしい上海風焼きそばが完成しますので、ぜひ参考に作ってみてくださいね。
上海風焼きそばとご一緒に! 粉ゼラチンが味の決め手の町中華風スープ
今回は、濃厚な味わいの上海風焼きそばにマッチする町中華風スープもご紹介していきます。超簡単なのにあるとうれしい、そんなスープもご一緒にいかがでしょうか。
材料(1人前)
- 粉ゼラチン……5g
- 鶏がらスープの素……小さじ1/2
- 醤油……小さじ1
- こしょう……適量
- 長ネギ……5g
- 熱湯……180〜200cc
町中華風スープの作り方

作り方は非常に簡単。長ネギを薄切りにして、お碗に熱湯以外の材料を全て入れます。

沸騰したお湯を注いで、しっかりかき混ぜればあっという間に完成です!

超簡単にできるスープですが、カギは「粉ゼラチン」にあります。
粉ゼラチンといえば、ゼリーなど冷たいデザートに多く使われる印象があると思いますが、その成分は動物性コラーゲン由来のタンパク質。熱いスープに加えると、味わいにコクとほんのりとしたとろみが加わり、まるでお店のような町中華風スープがたちまち完成するのです。ゼラチンはタンパク質の補給源としても期待されている食品ですので、ぜひ試してみてくださいね。

超簡単なスープですが、短時間で作ったとは思えない程に、時間をかけて煮込まれた鶏がらスープのような味わいを感じていただけると思います。少しだけとろっとしたスープは、うま味がしっかりと感じられ、あっさりしていながらも深みのある味わいになっています。
上海風焼きそばの濃厚な味わいを町中華風スープがマイルドにしてくれるので、ぜひセットで作ってみてください。
まとめ
今回は、上海風焼きそばと町中華風スープの作り方をご紹介しました。
上海風焼きそばは、おいしさを引き出すさまざまなコツをふんだんにお伝えしましたが、下準備は忙しさに応じて調節できるようになっています。できる範囲でお試しいただければと思います。それでは。
書いた人:美窪たえ
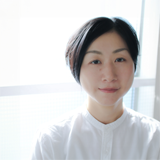
料理する人、食べる人。J.S.A.認定ソムリエ、SAKE DIPLOMA。OLからバーテンダー⇒日本料理人⇒フレンチコック⇒アメリカンデリという、異色の経歴を持つ料理家。料理のおいしさと酒への思いを発信するユニット[おとな料理制作室]としても活動。著書『おとな料理制作室へようこそ』(ワニブックス)が好評発売中。


