
こんにちは! 料理家の美窪たえです。
今回は、甘じょっぱく煮た油揚げと青ネギをとろとろの卵でとじてごはんにのせた「衣笠丼(きぬがさどん)」をご紹介します。
京都発祥といわれている衣笠丼は、ふっくらと煮た油揚げからジュワッと溢れるおだしがとってもジューシーで、お肉を使っていなくても満足感があります。

油揚げは大豆由来の良質なタンパク質が取れる上に、値段も手頃な食材。そんな油揚げをメインに、少ない材料と工夫でしっかり食べ応えがあるのに、短時間で作れるレシピになっています。
甘い油揚げととろけるような卵、青ネギの歯応えと食感も楽しむことができますよ。ぜひ丼物のレパートリーに加えてみてください!
材料(1人前)
- 油揚げ……2枚(約100g)
- ごはん……お好みの量
〈油揚げ用調味料〉
- だし……大さじ3
- みりん……大さじ2
- しょうゆ……大さじ1と1/2
- 酒……大さじ1
- 砂糖……大さじ1
〈仕上げ用〉
- だし(または水)……大さじ3
- 青ネギ(九条ネギ、ワケギなど)……1/2本分(約30g)
- 卵……2個
- 粉さんしょう……適宜

衣笠丼に最適な油揚げの選び方
まず、メイン食材である油揚げの選び方についてです。スーパーに並んでいる油揚げにはいくつかのタイプがあります。
一つは、おみそ汁やいなりずしなどでよく使われる薄揚げやすし揚げと呼ばれるもの。豆腐を薄く切って水分を抜いた後、油で揚げて作られるのが一般的です。
もう一つは、京揚げや手揚げ風などの名称で売られているものです。薄揚げより少し厚めに切った豆腐を油で揚げて作られており、豆腐の風味や食感を楽しむことができます。

今回のレシピでは、食べ応えを重視したいので後者のタイプがおすすめです。大豆由来の味わいがよく感じられ、ヘルシー感とうま味、食べ応えを兼ね備えているので、ぜひこちらの油揚げを選んでみてください。
ヘルシーでジューシーな衣笠丼の作り方

1.油揚げを3cm角にカットします。

2.油揚げに下処理をしていきます。油揚げは、おみそ汁に入れたり、焼いて食べたりする場合にはそのまま使うことが多いですが、煮る場合はひと手間かけて油抜きという下処理を行うと、味が早くよく染みふっくらとおいしく煮上がります。
そのままの状態の油揚げは、要するに揚げ物であるため、表面は油を吸っている状態。その油を適度に抜く(減らす)ことによって、調味料の染み込みが良くなることに加えて、カロリーを抑える効果もあります。
フライパンに水(分量外、400cc目安)を入れて中火にかけて沸かし、油揚げを入れて箸で沈めます。そのまま2分ほど茹でてお湯を切ったら、油抜きの完了です。

油抜きでカロリーを減らせる! と思うと、長時間お湯の中に置いておき、油を抜いてしまいたくなるところですが、油はうま味やコクといったおいしさの一部でもあるため、抜き過ぎてしまうと油揚げの持ち味までなくなってしまいます。
衣笠丼はお肉を使わない料理ですので、2分程度の茹で時間でほどよく油を減らすと、おいしさを活かしつつ、味の染み込みも良くなります。

3.フライパンをさっと洗ったら、〈油揚げ用調味料〉とお湯を切った油揚げを入れて中火にかけます。

4.沸いてきたら、ふたをして弱めの中火〜弱火で5分ほど煮ます。
厚みのある油揚げは元々煮崩れしにくいですが、卵でとじるので崩れたとしても問題ありません。

5.5分ほど経過したらふたを開け、上の面の色が白っぽければ裏返して火を止めます。これで油揚げの準備は完成です。
この時点で煮汁はほとんどなくなりますが、このくらいしっかり味を染み込ませた方が、ごはんと一緒に食べたときの味わいがちょうどよくなるのです。この状態でうどんにのせてもおいしいのでおすすめですよ。

6.油揚げが煮えたら、いったんふたをして置いておき、その他の具材の準備をします。
青ネギは、青い部分は7〜8mmに、白っぽい部分は5mmほどの斜め切りにします。九条ネギやワケギなど太めの青ネギを使うと、存在感があって食感も楽しめるのでおすすめです。

7.ボウルで卵を溶きほぐしますが、ここでポイントがあります。
そのポイントは、卵を混ぜ過ぎないことです。あえて白身と黄身のむらを残すように意識して混ぜると、見た目にも舌触りにも変化が出ておいしい卵とじを作ることができます。
勢いよく一気に混ぜるのではなく、白身を箸で持ち上げて切るようにしてほぐすのがコツです。白身がある程度ほぐれたら、最後に卵黄を軽く崩して終わりです。
白身はしっかり切っておかないと、ズルンと一気に鍋に入ってひと塊りになってしまうので、少し面倒に感じてもある程度ほぐしておき、最後にフレッシュな卵黄の黄色を残すことで、生き生きとした卵らしい色と絶妙な食感が同時に作れるのです。

8.油揚げと青ネギを卵でとじて仕上げていきます。
油揚げは煮汁を吸い込んで汁気がほぼなくなっていますので、〈仕上げ用〉のだし(または水)を加えてから中火にかけます。全体がグツグツとしっかり温まったら青ネギを加えて軽く混ぜ、まず卵の半量を回し入れます。

9.1分ほど煮て最初の卵が固まってきたら、残りの卵を全体に回し入れて10秒ほど煮て火を止めます。
このように、溶き卵を2回に分けて加えるのもおいしい卵とじを作るコツです。これだけでまるでプロが作ったような絶妙な卵とじに仕上げることができます。
親子丼、カツ丼、柳川丼など卵でとじる料理全般に応用のきく小技ですので、ぜひ試してみてください。

10.丼に温かいごはんを盛り付けます。
この間に、2回目に加えた卵にも適度に熱が伝わり、とろりと良い具合に落ち着いているはずです。

11.ごはんの上に、卵とじをふわりとのせれば衣笠丼の完成です!
ヘルシーでジューシーな衣笠丼の楽しみ方

卵が半熟のうちにいただきましょう! さじやスプーンがあるととても食べやすいですよ。一口頬張ると、油揚げからジュワッと甘じょっぱいだしが口の中に溢れてジューシーさを存分に感じることができます。食べ応えのある油揚げと滑らかな卵の舌触り、シャキシャキとした青ネギの香りと食感が絶妙です。

そして、京都で衣笠丼を食べるときの薬味として一般的なのが粉さんしょうです。うなぎを食べるときしか使わないという方も多いようですが、甘みのあるしょうゆ味には、もれなく好相性の和の万能スパイスです。お持ちであればぜひ試してみてください。味が引き締まって、どんどんさじが進みます。
まとめ

油揚げをジューシーに煮て作った衣笠丼をご紹介しました。
衣笠丼は京都発祥といわれていますが、京都以外の地域では、きつね丼やあぶ玉丼などとも呼ばれており、広く親しまれている料理です。手軽さと満足感がくせになるとてもおいしい料理ですので、ぜひぜひ試してみてくださいね。
書いた人:美窪たえ
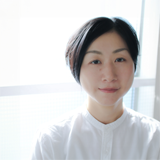
料理する人、食べる人。J.S.A.認定ソムリエ、SAKE DIPLOMA。OLからバーテンダー⇒日本料理人⇒フレンチコック⇒アメリカンデリという、異色の経歴を持つ料理家。料理のおいしさと酒への思いを発信するユニット[おとな料理制作室]としても活動。著書『おとな料理制作室へようこそ』(ワニブックス)が好評発売中。


