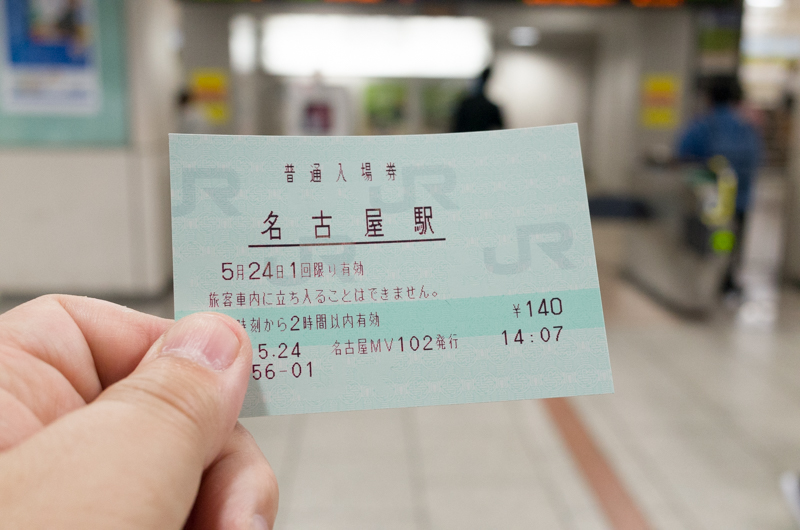名古屋のご当地ラーメン「ラーメン福」を知っているか
名古屋のご当地ラーメンというと、皆さんは何を思い浮かべるだろうか。
スガキヤ? 筆者も子どもの頃、よう食ったわ。ぜんざいソフトと一緒に。
台湾ラーメン? 名古屋で台湾とはこれいかに。しかも最近は「アメリカン」だの「イタリアン」だの。「まぜそば」だのいろいろ出てきてカオス。まあ、でも今じゃダントツの名古屋ご当地ラーメンだ。
しかし!!!!!
実は名古屋には、ほとんど地元民しか知らない&地元では絶大なる評判を誇るラーメンチェーンが存在する。
その名を「ラーメン福」と言う。

▲筆者の自宅から一番近い(なんだそりゃ)ラーメン福師勝店(北名古屋市)
現在、名古屋市内を中心に、愛知県下で10店舗が存在する「ラーメン福」。その店構えは共通している。
いかにも昭和の風情漂う(←褒めてる)店構え。レッドとイエロー(お店によってはレッドとホワイト)のビビッドなカラーリング。店内はカウンターのみの潔さ。そこに、ひっきりなしに現れるお客さんたち。

▲コの字型のカウンターが埋まるラーメン福 土古(どんこ)店。店内はどのお店もこんな感じ
開店と同時に席が埋まり、ランチタイムには待ちが発生する。
しかし店内はどのお店もカウンターのみだからか、お客さんの回転がめっちゃ早い!!そのため、意外と早く席につくことができる。

▲開店と同時にカウンターがどんどん埋まる
モヤシの存在感がハンパない
そして、店員さんがわっせわっせと運んでくるのは、山盛りのモヤシが強烈な存在感を放つラーメンたちだ。

▲ガンガン作ってガンガン出す!
これでも「ラーメン福」では“普通の”ラーメン。というわけで、野菜不足の人でもモヤシをわしゃわしゃ食べられる。
もはや食べているのが麺なのかモヤシなのか分からない。

▲モヤシがどっさり!「ラーメン福」の“普通の”ラーメン。しかし……
しかもそれだけではない。このモヤシ、注文時に「野菜多め!」という呪文の言葉を投げかけると、2倍近いボリュームの山盛りモヤシがトッピングされるのだ!
そのモヤシのインパクトは、まるで髪の毛が逆立ったスーパーサイヤ人である。

▲「ラーメン福」の魔法の呪文「野菜多め」。写真は早く撮らないとモヤシが重みに耐えかねて沈んでいく……
え、これってひょっとして二郎系なん? もしくは(二郎)インスパイア系なん?
そんな疑問が脳裏をよぎる。
しかし実は、二郎系とはな〜んの関係もない。名古屋で独自に発達したオリジナルの流派なのだ。
コクがあってマイルドな味わいの背脂醤油スープ。そして麺は、二郎系のような極太ではなくいたってスタンダードなストレート麺である。むしろ二郎系のような攻撃性はなく、昔ながらの「古き良き」ラーメンの風情すら漂わせる。

▲麺はストレートの中細麺。二郎系の極太麺とは一線を画する
そして、メニューがめちゃめちゃシンプル。
麺ものは「ラーメン」(600円)とチャーシューメンの「特製ラーメン」(800円)の2種類のみという潔さ。
あとは、ギョーザ(350円)とかライス(100円〜)とか、わずかなサイドメニューが用意されているだけだ。

▲「ラーメン福」のメニュー表。潔いほどシンプル(一部店舗では券売機)。そして水はセルフサービス
「ラーメン福」のラーメンは、一見すると(モヤシの量以外は)ごく普通のラーメンだ。しかし、なぜか妙な中毒性がある。一度ハマると抜け出せない“沼”ポイントは、「食べ飽きない」ことにある。
今回は地元民しか知らない名古屋のご当地ラーメン「ラーメン福」の世界をご紹介しようではないか。
専務に話を聞いてきた
さて今回、取材にうかがったのは名古屋市港区にある「ラーメン福 土古(どんこ)店」。
この店舗の2階に、ラーメン福チェーンを統括する「株式会社アライ」がある。

▲ラーメン福土古(どんこ)店。2階が株式会社アライのオフィス
出迎えてくれたのは、株式会社アライ専務取締役の大倉悦子さん。
創業者夫妻の娘さんで、「ラーメン福」の成り立ちから現在までの歴史を知る、貴重な存在といえる。

▲話を聞いた専務の大倉さん。「私こんなガラじゃないですよ〜」という言葉を振り切って「イエ〜」と(無理やり)はしゃいでいただいた
まずは、「ラーメン福」の成り立ちから、じっくりと話を聞かせてもらった。
大倉さんによれば、「ラーメン福」のオープンは昭和53年4月のこと。現在の十一屋店(名古屋市港区)が1号店に当たる。
昭和53年といえば、今年(2018年)でちょうど40周年を迎える。名古屋民としては実にめでたいことではないか。

▲開店当時の十一屋店。昭和を感じさせるが基本イメージは変わらない
 十一屋店は、私が中学2年生のときにオープンしたんです。当時は両親と、数人のパートさんだけのお店でした。
十一屋店は、私が中学2年生のときにオープンしたんです。当時は両親と、数人のパートさんだけのお店でした。
と、見せてくれた開店当時の写真は、ビックリするほどタイムラグを感じない「福っぽさ」が見て取れる。
40年間ここまでオリジンのテイストを受け継いでいる(しかも陳腐化しない)のは、もはや名古屋ラーメン界の生ける伝説である。


▲開店当時の十一屋店の外観と店内。ビックリするほど今の雰囲気と変わらない。ちなみに開店祝いの花を客が持ってくのは名古屋の風習である
ルーツは京都のしにせラーメン店のFC
さて、「ラーメン福」は開店当時は「ラーメン藤」という店名だったことは、オールドファンの中でも遠い過去の記憶となる。
しかし「ラーメン藤」と聞いて、ラーメン通ならピンとくる人もいるだろう。実はこの「ラーメン福」、元々は同名の京都のしにせラーメン店「ラーメン藤」のフランチャイズだった。脱サラした創業者(大倉さんの父)が京都の本店でラーメン作りを学び、名古屋で開店したのだった。
こちら、京都の「ラーメン藤 本店」。
この味は、京都生まれの名古屋育ちというわけだ。開店当時はタレを京都の本店から仕入れ、麺は岐阜の系列の製麺所で仕入れていたそうだ。
フランチャイズだけあり、当時は京都の味に忠実だったそう。しかし、転換期が1989年(平成元年)に転機が訪れる。
 麺やスープを内製化することになり、平成元年の法人設立をきっかけに、グループを離れることに。そのとき、店名を『藤』から『福』に改めたんです。
麺やスープを内製化することになり、平成元年の法人設立をきっかけに、グループを離れることに。そのとき、店名を『藤』から『福』に改めたんです。
そこから、独自の道を歩み始めた「ラーメン福」。
ちなみに現在の「福」と「藤」のラーメンを比べてみよう。こちら、現在のラーメン福のラーメン。

そしてこちら、現在の「ラーメン藤 本店」(京都)。
確かに約30年で、似て非なるラーメンに分化している。
ちなみに「新福菜館」といい「天下一品」といい「横綱」といい、なぜか京都発祥で有名どころのラーメンはこってり風味が多いんだよなあ。「京都人は薄味じゃないのかよ」と妙な疑問が沸くのだが、それは今回のお題には関係ない……(以上、筆者の独り言)。
味のヒミツは羽釜でスープを炊くときの“グラグラ感”
そんな「ラーメン福」だが、実は根幹部分はシッカリとルーツの伝統を守っている。
スープを炊くのは、“京都式”のおくど(かまど)に3連星のように並んだ、熱効率の良い羽釜。これで朝から豚肉と背脂、そして野菜をグラグラと煮込んでいる。

▲昔から変わらない、「京都式」3連のおくど(かまど)と羽釜
この“グラグラ”が実は重要で、バーナーの火力で独特のコクとうま味がでる。それが、「ラーメン福」のスープのキモだ。

▲スープを羽釜でグラグラと煮込む。ひたすら煮込む

▲背脂が溶け込んだ醤油スープ
ちなみにスープは各店で仕込んでいるので、お店ごとに微妙な「個性」が出るという。だからコアなファンになると、お気に入りの職人さんが作ったお店に出入りするようになる。
たまにお店の配属が変わると、その職人さんを追っかけるファンもいるとかいないとか……。
推しメンか!!
魔法の呪文「野菜多め」はあくまでサービス
さて、「ラーメン福」の代名詞といえば、ボリューム満点のモヤシである。
普通にオーダーしても山盛りなのに、多くのお客さんは口々に「野菜多め!」とオーダーし、トングでモヤシがどーんと盛られてバンバンお客さんの前に出される光景は、圧巻だ。
しかも「野菜多め」でも、料金は同じ。無料サービスである。二郎系が名古屋に進出するはるか昔から、名古屋ではこんな光景が当たり前だったのだ。

▲トングでモヤシをつかみ、ドーン!と盛る。ちなみに「野菜少なめ」も当然できる
でも、何かおかしい。メニューのどこにも「野菜」の記述はないのだ。
大盛りにできるとも書かれていない。それでもお客さんは「野菜多め」と、当たり前の権利主張のようにオーダーする。
 当店のラーメンは、普通でもモヤシの量が200グラム以上あって、十分多めです。ですから私の友達にも、開店当時から『モヤシラーメン』って呼ばれてました。
当店のラーメンは、普通でもモヤシの量が200グラム以上あって、十分多めです。ですから私の友達にも、開店当時から『モヤシラーメン』って呼ばれてました。
確かに言われてみれば、京都の「ラーメン藤」も野菜(モヤシとネギ)が多そうだ。
その流れを当然受け継いでいるわけだから、そもそもモヤシが多いというのは当然と言えば当然だ。
 20年くらい前からですかね。お客様の中で「追加料金を払うから、モヤシを増やしてくれ」という方が現れたんです。それで、そういう方には無料サービスでモヤシを多めにしてあげていました。それが口コミで広がって、いつの間にか「野菜多め」が当たり前になっちゃって……(笑)。
20年くらい前からですかね。お客様の中で「追加料金を払うから、モヤシを増やしてくれ」という方が現れたんです。それで、そういう方には無料サービスでモヤシを多めにしてあげていました。それが口コミで広がって、いつの間にか「野菜多め」が当たり前になっちゃって……(笑)。
なるほど。
「野菜多め」は、あくまでサービス。
だから、メニューには載ってない……。 _φ(・_・メモシテオコウ。

▲野菜のボリュームは「モヤシ少なめ、ネギ多め」などトリッキーなオーダーもOK
ちなみに「野菜多め」でのモヤシの量は、350グラムほどになるのだそう。ただそうなると、やっぱり聞きたいのは「どこまで野菜多めにできるの?」ってことだ。
 実は一時期エスカレートして「別皿でモヤシが欲しい」というお客様まで現れたんです。それはさすがにキツいので、お断りさせてもらいました。
実は一時期エスカレートして「別皿でモヤシが欲しい」というお客様まで現れたんです。それはさすがにキツいので、お断りさせてもらいました。
いやー、いつの時代にもいるんだなぁ、そういうお客さん……。
ラーメンダレは何のためにあるのか
「ラーメン福」のカウンターには「ラーメンダレ」が置いてある。最近の二郎系ラーメン店にもよくあるアイテムだ。
普通は「味が薄いと感じた時に、かけて調整する」のが用途。しかし、「ラーメン福」はちょっと事情が違うという。

▲カウンターに置かれているラーメンダレ(左から2番目)
実は、大倉さん自身は
 味のバランスを考えると、(野菜大盛りじゃなくて)普通盛りの方がおいしく食べられると思うんですけどね〜。
味のバランスを考えると、(野菜大盛りじゃなくて)普通盛りの方がおいしく食べられると思うんですけどね〜。
と、ミもフタもないことをおっしゃる(大汗)。
当たり前だけれどモヤシ自体には味がない。だから、モヤシの水分でスープの味は薄くなりがちだ。
それが「野菜多め」になると、余計のことだ。

▲当然、モヤシには味がない。モヤシが多いほど水分で味が薄まる
じゃあどうする、ということで登場したのが、カウンターに置かれているラーメンダレというわけだ。モヤシでスープが薄くなるのを、ラーメンダレで味を足すことで防ぐ。つまりは、「野菜大盛り」によって味が薄くなる弊害を解消する、苦肉のアイテムだったのだ。
おいしい食べ方をレクチャーしてもらう
以上の情報を踏まえ、おいしいラーメン福の食べ方を、直接レクチャーしてもらおう。
大倉さんいわく、「ラーメン福」のラーメンは、麺とモヤシを別々に食べるのではなく「麺とモヤシを一緒に食べるのが一番おいしい」そうだ。

▲中細麺とモヤシだからこそのコンビネーション。これが「ラー福」の極意!
二郎系のゴワゴワ太麺と違い、「ラーメン福」の麺はあくまでスタンダードなストレートな中細麺。小麦粉麺のシコシコした食感に、モヤシのシャキシャキした食感が加わり、「ラーメン福」のうまさがある。
そして、麺とモヤシの太さが近い。だから、一緒に食べても違和感がないのだ!
しかし問題は、麺の上にうず高く積み上げられたモヤシである。モヤシが麺の出現を邪魔しているのだ。なんとか、麺を上まで引き上げねばならない……!
そこで、大倉さんから的確なアドバイスが!!
 私は、モヤシをレンゲで押さえて(山を崩れないように固定し)、モヤシの下から麺を引っ張り出してモヤシの上にのせるんです。こうすると、麺についたスープの味がモヤシにも染み込むので、さらにおいしいですね。
私は、モヤシをレンゲで押さえて(山を崩れないように固定し)、モヤシの下から麺を引っ張り出してモヤシの上にのせるんです。こうすると、麺についたスープの味がモヤシにも染み込むので、さらにおいしいですね。
なるほど。
と、いうわけで、大倉さんに直々に実演してもらった。
youtu.be
この技は、
 特に名前はありません(笑)。
特に名前はありません(笑)。
とのことなので、“固めてひっくり返す”という意味を込めて「モヤシスープレックス」とでも名付けてしておこう。
この技のポイントは、なるべく早めに麺を引きずり出すこと。麺がスープを吸って重くなると、麺を引きずり出しにくくなるのだ。

▲麺がスープを吸う前に、モヤシの下から麺を引きずり出す
そのほか、上級者には二郎系でもおなじみの「天地返し」もいい。麺とモヤシをひっくり返すことで、モヤシがスープを吸っておいしく食べられるとのこと。
この技はなぜか、「ラーメン福」の公式サイトでも紹介されている。
ただし大倉さん自身が
 私、あんまり上手にできないんですよ(笑)。
私、あんまり上手にできないんですよ(笑)。
と言うくらいなので、多少のテクニックが必要とされる。
youtu.be▲公式サイトでも紹介されている「天地返し」
そのほか、筆者のオススメはモヤシの中央に穴を開けてそこから麺を引っ張り出す技法である。これはこれで、麺をほじくり出す前にチャーシューが出てきたりして、宝探しのような面白さがある(どこがだよ)。
こちらは個人的に動画にアップ。
「ドーナツスペシャル」とでも言っておこうか(すまんネーミングセンスが……)。
youtu.be▲モヤシの中央を突破して麺をレスキューする。しかし先に出てくるのはチャーシュー(笑)
胃袋を刺激する脇役も見逃せない
「ラーメン福」にはサイドメニューもある。オールスターを紹介しておこう。
スタミナ辛子


▲スタミナ辛子は入れる量に注意。一気に入れると味が変わりすぎる??
(かつての)京都本店にもあった唐辛子の薬味を独自に改良した、大倉さんのお母さん(=創業者)によるオリジナル。唐辛子やニンニク、ダシなどいろいろなものが入った、辛くて奥深い味わいだ。ラーメンの味が単調になったところに投入すると、ぐっと味が引き締まる。
 当時は、母が自宅の台所で作っていました。
当時は、母が自宅の台所で作っていました。
ちなみにこのスタミナ辛子、350円で販売もしている。名古屋みやげにいかが?
ギョーザ


▲普通だけどうまい。それはラーメンもギョーザも同じ。これぞ福マジック!
ギョーザ(350円)は、前日に収穫された愛知県田原市産などのキャベツ、青森県産のニンニクなど鮮度のいいものを使用。肉多めでジューシーだ。中身のあんは土古店で集中して作り、各店で包んでいる。
チャーシュー
(通常の)ラーメンに入っているのはモモ肉のチャーシュー。
ほぐれているので、麺やモヤシと一緒に口に入る。味を複雑にする第3のアイテム。

▲こちら、ラーメンに入るモモ肉のチャーシュー

▲ラーメンに入るとこんな感じ。麺とモヤシとチャーシューのコラボ、これでまずいワケがない
かたや、特製ラーメン(チャーシューメン)に入っているのは、雌豚限定の肩ロース。こちらはシッカリした肉質で、食べ応えがあるのが特徴だ。
この肩ロースとモヤシを盛り付けたおつまみ「チャーシュー盛付」(500円)は、一人じゃちょっとツラいくらいのボリュームだ。

▲特製ラーメン(チャーシューメン)に入る肩ロースのチャーシュー。歯応えしっかりで食べ応えあり

▲こちら、おつまみの「チャーシュー盛付」(500円)。肩ロースとモヤシのボリュームがハンパない!グループで1つオーダーするのが正しい
玉子

▲玉子は玉子なので写真としてはどう面白そうに撮影しても玉子である
玉子(50円)はカウンターの上のザルにあり、セルフサービスで。
いたって普通のゆで玉子だが、そのまま食べても、ラーメンに入れても、ご自由に。なお店舗によっては、生玉子を提供しているところもある。生玉子を入れたら麺やモヤシに絡んで、新たな味のステージになる(かもしれない)。

▲とりあえずラーメンの中に入れてみた
幻の(?)テレビCMについて聞いてみた
実は公式サイトによると、「ラーメン福」はテレビCMを放映している。
しかし名古屋在住の筆者自身、そんなCM、見たことないのだ。いったいいつ放送しているのかを大倉さんに聞いてみた。
 あのCMは、スポット放送なんです。ですから、いつ放送されるとは言えないんですね。比較的多いのは年末年始。ランダムに入るので時間も分からないです。
あのCMは、スポット放送なんです。ですから、いつ放送されるとは言えないんですね。比較的多いのは年末年始。ランダムに入るので時間も分からないです。
うーむ。「見ることができた人には、幸せが舞い込んでくる」的な、都市伝説的なアレだと思った方がいいのだろうか。
ちなみに公式サイトで、そのCMは見ることができる。
youtu.be▲公式サイトには3つのTVCMが紹介されている
マスコットキャラクターについても聞いてみた
「ラーメン福」のマスコットキャラクターの名前は、そのまんま「福ちゃん」だ。お店の看板などで、丼を片手にスマイルを振りまいている。

▲福ちゃん(師勝店にて)。ちょっと萌えキャラ
実はこの福ちゃん、数年前、2代目にリニューアルしてちょっとカワイクなったそうだ(鬼太郎の猫娘か!)。
しかし2018年現在、お店の看板は、改装のタイミングで初代と2代目の福ちゃんが混在しているという。お店ごとに福ちゃんチェックをするのも面白そうだ。
 ちなみにLINEスタンプもありますよ! ぜひ利用してください。
ちなみにLINEスタンプもありますよ! ぜひ利用してください。
「ラーメン福」は当分、愛知県限定
そんな「ラーメン福」の今後は、どうなっていくのだろう? 東京進出などは考えているのだろうか。
 2013年(平成25年)に、のれん分け店舗「黄金店」(名古屋市中村区)が出店しました。ただ、のれん分けはできてもフランチャイズはできないです。スープの仕込みをマスターした人でないと、同じ味が出せませんから。
2013年(平成25年)に、のれん分け店舗「黄金店」(名古屋市中村区)が出店しました。ただ、のれん分けはできてもフランチャイズはできないです。スープの仕込みをマスターした人でないと、同じ味が出せませんから。
こちら、その黄金店。のれん分けということで、直営店とは少しカラーリングが異なって赤と白が基調。
 ただ、今後はのれん分けの店舗が増えていくことになると思います。愛知県内でいえば、来年(2019年)に三河エリアで初めて開店を予定していますよ!
ただ、今後はのれん分けの店舗が増えていくことになると思います。愛知県内でいえば、来年(2019年)に三河エリアで初めて開店を予定していますよ!
喜べ三河民! 平成が終わる頃には、三河で「ラーメン福」が食べられるぞ!!!
他県民の方々は、すいませんが愛知に来てください(っても、ちょっと郊外にしかないんだよな……笑)。
ちなみに名古屋南部の「ラーメン福」分布を見ると、まるでケンシロウの「胸の七つの傷」のように見えるのは筆者だけだろうか……。
▲南部の支店に注目。わからなかったらここはスルーしてくれ
「40周年 至福祭」を見逃すな!
ちなみに「ラーメン福」では、6月22日(金)〜24日(日)の3日間、「40周年 至福祭」を開催する。

▲40周年の「至福祭」のポスターがこちら
ここでは、回数券(ラーメン11杯)を5,500円で販売。
超お得だ!
また、麺類1杯につき1枚スクラッチカードがプレゼントされ、「ラーメンを40日間無料で食べられるパスポート」(!!)などプレゼントが進呈される。詳しくは以下の公式サイトを参照のこと。行かない理由はないはずだ。
ra-menfuku.com
お店情報
ラーメン福 土古店
住所:愛知県名古屋市港区川西通3-9
電話番号:052-653-1587
営業時間:11:00~23:00
定休日:火曜日
www.hotpepper.jp
書いた人:イシグロアキヒロ

名古屋を拠点に活動するフリーライター。カリブ海音楽と台湾ラーメンとキンキンに冷えたビールと朝ドラ「カーネーション」とハロプロをこよなく愛する。
過去記事も読む